開田村民と林野との関わりについては、複雑な変遷をたどって現在に至っています。
この項は、開田村誌をもとに簡略にまとめてみましたが、割愛した部分が多くあります。
村誌においては膨大な頁を割いて、林政についての記述や関係文書の掲載があります。
したがって下記のまとめについては、説明不足な所、解り辛い所、抜けている所等があると思いますが、悪しからずご了承下さい。
標高3,067mの木曽御嶽山を西南に控え、その山麓の裾野に広がる広大な高原地帯、村落の全てが標高1,000mから1,200mにおよぶ高地に点在する開田村は、まさに典型的な山村です。
昔から住民は、山によって生きてきました。
狩猟、山菜取り、焼畑や切畑と称する原始的農業、家畜の放牧、飼料肥料としての草刈り、燃料としての薪伐り・炭焼き、住居の建築用材まで、開田村の住民の生活は、深く山林に依存してきました。
民俗、文化、民謡にいたるまで、山を離れて開田村を語る事は出来ません。
古くから木曽は森林資源が豊富でした。
平安時代、庄園の発生以来木曽は常に中央権力の直轄の支配地となり、一時期、地方豪族木曽氏の支配下におかれたものの、天下を制した豊臣秀吉は、自らの直轄地として代官を置き支配させました。
引き続き江戸時代は徳川尾張藩領となり、明治から今日までは天皇又は国の所有直轄として支配されてきました。
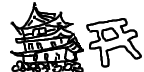 大事な宮、寺、城、居館などの用材が木曽の山から伐り出されました。
大事な宮、寺、城、居館などの用材が木曽の山から伐り出されました。
伐り出した記録をあげれば枚挙にいとまがありませんが、その一部をあげると、皇大神宮、豊受神宮、大仏殿、聚楽第、大阪城、江戸城、駿府城、名古屋城などがあります。
江戸時代以前の木曽住民は、木年貢を中心に雑穀などの年貢を納め、生活に必要な部分の林野利用に関しては比較的自由であったようです。
その頃までは木曽の山村に住む人口は僅かで、地元住人が必要な木材を伐ったり、ところどころ切畑焼畑を開墾しても、資源保全の妨げなどの問題にはならなかったようです。
豊臣時代を含め、江戸時代に入り、城の改築、寺・宮の造営、城下町といったの近世都市の建造などが盛んになり、それらに必要な木材の需要が全国的に高まりました。
その需要に対応する為、搬出に不便な遠地の山林までが濫伐、過伐の対象となりました。
その後、徳川尾張藩は、山林保護を重視し巣山・留山という制度を作って、その区域内への住民の立ち入りを禁止しました。
また、巣山・留山の保護のため、山火事の原因となる焼畑・切畑についても、厳重な制限が加えられました。
 「巣山」とは、戦国大名が鷹狩りを好み、鷹が巣をかける奥山を巣山と称して、みだりに立入り伐採を禁止した事から始まっています。
「巣山」とは、戦国大名が鷹狩りを好み、鷹が巣をかける奥山を巣山と称して、みだりに立入り伐採を禁止した事から始まっています。「留山」とは、1664年に尾張藩が木曽山の巡検を行った際にその荒廃に驚いて林政改革を行い、伐り残された美林をすべて留山として人民の立入り伐採を禁止したものです。
巣山でも留山でもない山地は明山と呼ばれ、木年貢を納めて地元住民が自由に入山利用していました。
しかしその後、特定の樹種について、停止木・留木という制度で伐採の禁止が行われるようになりました。
「停止木」は、ひのき・さわら・ねずこ・あすなろ・こうやまき(木曽五木)、「留木」は、まつ・くり。
更に、その他の木の伐採利用にも届け出が必要な時期もありました。
土地は全て藩領である、という封建制度の時代でしたが、江戸中期以降、山村地域における集落の発達につれて、林野の恒常的利用度が高まりました。
従来のような明山に対する厳しい利用制限は、林野の利用以外に営農も生活も成立たない山村住民の現実に沿わなくなり、次第に変化しました。
明山の内でも雑木が疎生して原野の相をなしている地域は、肥飼料、薪炭、用材の供給源として、付近の集落集団によって恒常的に利用されるようになります。
それらの地域は、従来の明山に対する一般的入会権よりも、部落集団による団体的権利、または有力な個々の農家が独占的に用益する権利が定着するようになりました。
入会林野は、地域の住民がその生活を営むために、自主的規制のもとに林野を利用してきた長年の慣行が、藩領主によって公認されたことから成立したといわれています。
生計維持に欠く事の出来ない重要な物であったので、入会林野に対する住民の団結は固く、他の集団に対しては極めて排他的でした。
▼
次へつづく